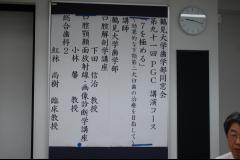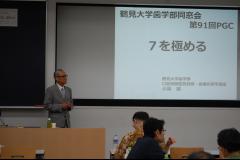鶴見大学歯学部同窓会
〒230-8501
神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3
TEL:045-581-1080
FAX:045-582-8929
災害時情報提供専用メールアドレス
アクセスマップ
平日 9時30分~17時00分
土・日・祝日はお休みになります。
〒230-8501
神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3
TEL:045-581-1080
FAX:045-582-8929
災害時情報提供専用メールアドレス
アクセスマップ
平日 9時30分~17時00分
土・日・祝日はお休みになります。
- Tweet
第91回PGC(第1回目)開催報告
2015年9月24日(木)掲載
今年度のPGCは、鶴見大学歯学部同窓会学術部門の変化の年とするべく、例年とは異なり、1年間にわたり「7を極める」という1つのテーマに沿った全3回のミニレクチャーを開催することとなった.対象となる受講生は臨床経験の浅い若手の歯科医師で、日常の診療ですぐに使えるような臨床に特化したレクチャーを目指した.下顎7番の治療はドクターを悩ますことが多いせいか、全3回の受講申し込みはあっというまに定員に達した.第91回PGCは、7月26日(日)、鶴見大学記念館2階第1講堂において開催され、30度を超える猛暑にもかかわらず、25名の受講生が参加した.レクチャーは3部構成で、解剖学→読影→歯内療法の順で進行した.司会は、学術理事寺田知加、学術委員小佐野貴識が担当した.① 解剖:口腔解剖学講座 下田信治教授(5期)
下田教授には、下顎7番に関する発生学や組織学からみた歯冠・歯根の位置関係や形態のバリエーション、う蝕の進行や歯周組織の特徴を説明していただいた.臨床に必要な要点を簡潔にお話ししていただいたため、容易に理解することができた.また、普段は見ることのできない歯の標本も実際に供覧していただいたので、改めて下顎大臼歯の複雑な構造を実感できた.
② 読影:口腔顎顔面放射線・画像診断学講座
小林 馨教授(5期)
下顎7番は、デンタルの撮影ではフィルムの位置付けが困難であり、嘔吐反射が誘発されやすく、周囲の様々な構造物と重なりやすいために読影も難しい.小林教授には、下顎7番のデンタルX線を上手に撮影するためのコツ、樋状根の見分け方、CBCTとデンタルとの比較をレクチャーしていただいた.
③ 歯内療法学:総合歯科2紅林尚樹臨床教授(8期)
紅林臨床教授には、実際の臨床で有用な診断学、隔壁の作り方、アクセスホール形成のコツ、根管洗浄で有用な器材の紹介、難治性感染根管への対応などを講演していただいた.解剖学、読影のレクチャー後ということもあり、受講生にとって理解しやすく、臨床ですぐに応用できる内容であった.
質疑応答では、受講生が持参した症例をもとにディスカッションを行ったり、講師同士でも質問をしあう場面もあった。最後に、高橋宏嘉副会長より、講師の先生方に感謝状が贈呈され、本PGCは盛会のうちに終了した.
アンケートの結果は下記の通りです。
1. 今後取り上げてもらいたいテーマ、あるいは講師
・義歯の配列と調整の仕方を詳しく
・ハンズオンやってほしい。解剖をやりたい
・訪問歯科
・漢方の臨床
・顎堤が著しく吸収した状態の義歯製作・調整のポイント等(特に下顎)
・ハンズオン、解剖実習、少人数でいいので予約制でして欲しい
2. その他、感想、ご意見等ございましたらお聞かせください。
・基礎から臨床にかけて網羅されていてわかりやすかった
・8をExtして7の遠心歯頚部下からの方治療ができない!
(接触したところ)カリエスになってるのに・・
・簡単に細菌検査なんて出来ない
コメントの閲覧にはログイン(会員登録)が必要です。
ログインする
ログインする
最新記事
|
第107回PGC開催報告 「口腔顎顔面領域の痛みへの対応」 2025年12月2日(火)掲載
|
|
第106回PGC開催報告 「歯周外科治療のアップデート」 2025年4月16日(水)掲載
|
|
第105回PGC開催報告 「より安定した接着性修復を求めて」 2024年10月21日(月)掲載
|
|
第104回PGC開催報告 「バイタルサインの基礎の基礎!歯科で発生する全身的偶発症への対応」 2024年7月16日(火)掲載
|
|
第103回PGC開催報告 「抜歯か非抜歯か?矯正歯科治療における治療目標設定までのプロセスの再考」 2024年2月19日(月)掲載
|